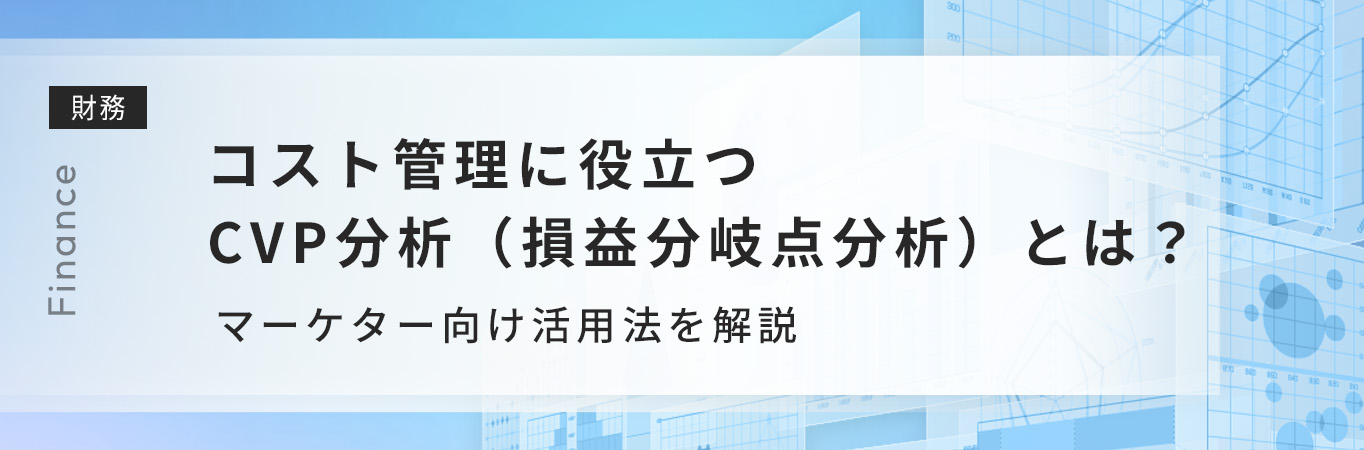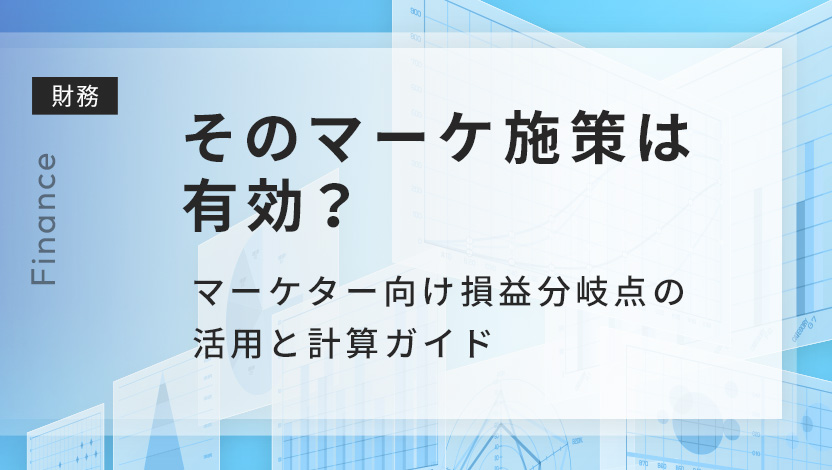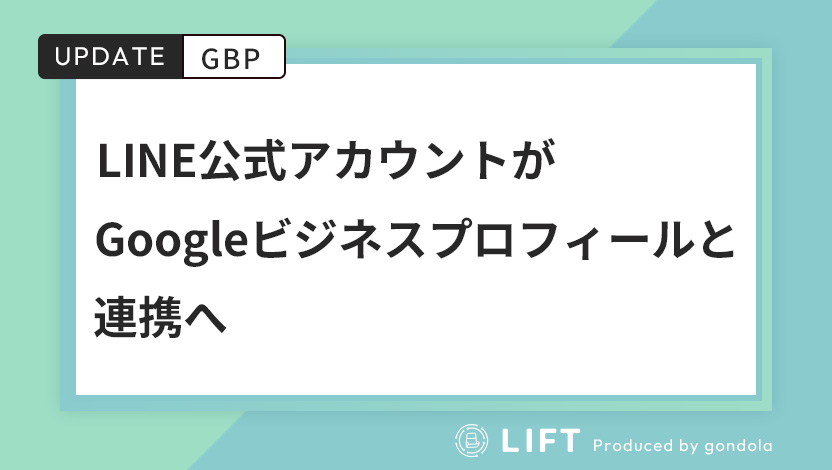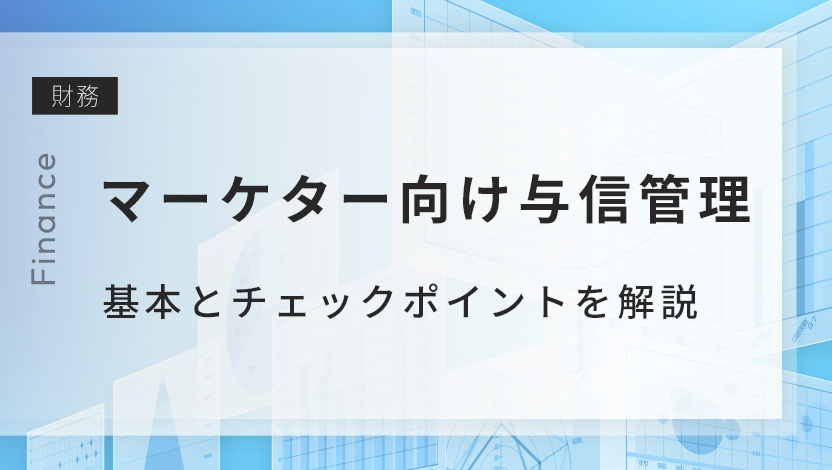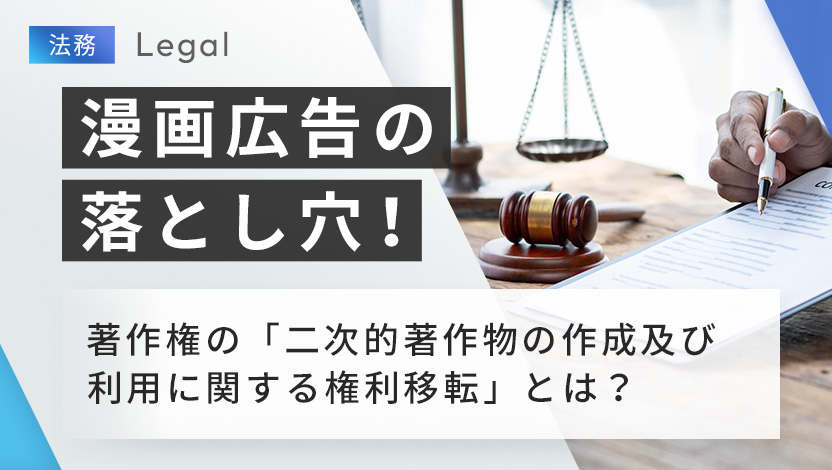CVP分析とは、コスト・販売量・利益の関係を把握できる分析手法です。
マーケターがCVP分析を活用することで、マーケティング施策により見込まれる売上に対して、利益を最大化するための最適なコスト配分や販売価格を決める基準となります。
本記事では、マーケターがCVP分析を活用できるよう、CVP分析に必要な基礎知識と指標、簡単な計算方法などを解説します。
INDEX目次
CVP分析とは?コスト・販売量・利益から算出するもの
CVP分析とは、コスト(Cost)、販売量(Volume)、利益(Profit)の関係を明らかにする分析手法です。この分析では「損益分岐点」を算出することが前提となるため、「損益分岐点分析」とも呼ばれます。
CVP分析は企業の財務分析によく用いられますが、マーケティングの適切な予算や戦略、施策の目標を設定するために、マーケターも知っておいたほうが良い分析手法です。
CVP分析の前提となる損益分岐点とは
CVP分析を行うためには、まず、損益分岐点について押さえておく必要があります。
損益分岐点とは、売上高=費用(コスト)となる金額のこと。
損益分岐点では売上ー費用=0となり、利益も損失も発生していません。損益分岐点を売上が下回ると損失が生じ、損益分岐点を売上が上回ると利益が生じます。
CVP分析では、損益分岐点を算出したうえで、コスト・販売量・利益の関係についていくつかの指標から分析を行います。これにより、利益を増やしていくためのコストと販売量のバランスを把握できます。
損益分岐点について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。
CVP分析で達成できる4つの目的
CVP分析を行う大きな目的として、以下の4つがあげられます。これらは、CVP分析を行うメリットともいえます。
利益の最大化
事業の成長には売上だけでなく利益の確保が重要です。売上だけを見ていると、売上は増えたもののその分コストも増え、利益が増えていないという事態になりかねません。
CVP分析を行うことで、売上の増減、すなわち販売量の増減に対するコストと利益の動きがわかります。これにより、どこまでコストをかけ、どのくらいの販売量があれば利益が最大化するのかがわかります。
また、商品・サービスごとのCVP分析を比較することで、利益を最大化するために注力すべき商品・サービスが見えてきます。
コストの最適化
CVP分析では、商品・サービスを販売するためにかかるコストについて、どのようなコストがどのくらいかかっているのか、コストを分類して内訳を明確にします。
これにより、利益を増やすために削減したほうが良いコストと、販売量を増やすためにもっとコストをかけたほうが良い部分がわかり、コストの最適化につながります。
コストの分類について、詳細は後述の「CVP分析に必要な指標と簡単な計算方法」の「固定費と変動費」で解説しています。
リスクの予測と対策
CVP分析を定期的に行うことで、コスト・販売量・利益のバランスの変化に早めに気づくことができます。
コストの増加や販売量の低下など、利益が減る兆しに早めに気づくことで、大きな変化が起こる前にリスクを予測して対策を立てることができるはずです。
また、事業ごとにCVP分析を行うことで、事業ごとのリスクの高低もわかり、リスクの高い事業が大きな損失を出す前に対策を立てることもできます。
投資判断の材料
CVP分析を行うことで、商品・サービスや事業について、コストをかけることでどれだけの利益を得られる可能性があるのか、数値化できます。
これにより、できるだけ利益が大きくなる可能性が高い商品・サービスや事業へコストをかける判断ができます。
また、実際にかけたコストがどれだけの利益に結びついたのかの評価もできます。
CVP分析に必要な指標と簡単な計算方法
CVP分析では、以下の指標が必要となります。これらの指標を順番に求めていくことで、CVP分析ができます。
ここでは、各指標から読み取れることと、簡単な計算方法を解説します。
固定費と変動費
CVP分析では、まず、商品・サービスを販売するまでにかかる費用(コスト)を「固定費」と「変動費」に分類します。これを「固変分解」といいます。
固定費とは、売上高に関わらず常に一定の期間で発生する費用のことです。たとえば、家賃や人件費、広告宣伝費などが固定費にあたります。
変動費とは、売上高に比例して増減する費用のことです。たとえば、商品の原材料費やサービスの販売手数料などが変動費にあたります。
費用の割合が固定費<変動費の場合、売上が小さい段階でも利益が出やすい一方で、売上が増えても利益は増えにくい構造です。
逆に、費用の割合が変動費<固定費の場合、売上が小さいと利益も小さいですが、売上が増えるにつれて利益が増えていく構造です。
限界利益と限界利益率
「売上高-変動費」で求められるのが「限界利益」です。限界利益のなかには、固定費も含まれています。
「限界利益率」は、売上高に占める限界利益の割合を示します。計算式は「限界利益÷売上高×100」です。
限界利益率が高い商品・サービスは、売上が増えると利益も増えやすい状態です。そのため、商品・サービスごとの限界利益率を比較することで、売上向上に注力すべき商品・サービスが見えてきます。
ただし、限界利益における固定費の割合が大きい場合は、いくら限界利益率が高い商品の売上が増えても利益は増えにくい状態です。限界利益・限界利益率を求めるときは、固定費も明確にしておきましょう。
損益分岐点と損益分岐点比率
損益分岐点は、「固定費÷限界利益率」で求められます。なお、これは損益分岐点を売上高で求めたもので、販売数量で求める方法もあります。
損益分岐点比率は、売上高に対する損益分岐点売上高の割合を表します。計算式は「損益分岐点売上高÷売上高」です。
基本的に、損益分岐点は低いほど良いとされます。これは、損益分岐点が低いほうが、売上が下がっても赤字になりにくいからです。別の言い方をすれば、固定費に係る投資を早期に回収できる、ともいえます。
一般的な目安として、損益分岐点比率は80%未満が良いとされます。
安全余裕率
安全余裕率は、実際の売上高が損益分岐点をどれくらい上回っているかを示す指標です。「(売上高-損益分岐点売上高)÷売上高×100」で求められます。
一般的な目安として、安全余裕率は20%以上あったほうが良いとされます。さらに、安全余裕率が40%以上あると優良な経営状態とされます。
ちなみに、損益分岐点比率と安全余裕率は、足すと100%になる関係です。
マーケティング現場でのCVP分析の3つの活用法
マーケティング現場においてCVP分析を活用するには、まず、損益分岐点表を作成するとわかりやすいはずです。
損益分岐点表については、以下の記事の「損益分岐は図表にするとわかりやすい」の説明を参考にしてください。
そのうえで、マーケティング現場におけるCVP分析の活用法として、以下のような方法があります。
施策にかけて良いコストの判断
マーケティング施策を立案する際、CVP分析を行うことで、見込まれる売上に対してどこまでコストをかけて良いか判断できます。
多くの場合、マーケティング施策にかかるコストは、広告宣伝費として固定費に分類されます。広告宣伝費とは、不特定多数の人に広告媒体などを使って間接的に、商品・サービスを訴求するためにかかる費用のことです。
コストが増えるということは、損益分岐点が上昇するということです。つまり、利益を出すためにはより多くの販売量が必要となります。
さらに、コストのうち固定費の割合が増えるということは、売上が小さいうちは利益が出にくいものの、売上が大きくなるにつれて利益が増えやすくなるということになります。
なお、購入者プレゼントなど、売上に連動してコストが増える施策の場合、そのコストは変動費に分類されます。コストのうち変動費の割合が増えると、売上が大きくなっても利益が増えにくくなります。
その場合、利益を増やすためには、できるだけコストを抑えるか、獲得した顧客にリピートを重ねてもらって中長期的に利益を増やせるような施策の設計を行う必要があります。
利益を確保できる販売価格の決定
利益を増やすための基本は、コストを抑えながら販売量を増やしていくことです。それでも思うように利益が増えない場合は、販売価格を上げる必要があるかもしれません。
CVP分析を行うことで、コストと販売量が同じで販売価格が異なる場合、利益にどのような違いが出るかを比較できます。これは、新商品の販売価格を決定する際や、既存商品の販売価格の見直しをする際に役立ちます。
CVP分析を取り入れることで施策の説得力が増す
マーケティング施策の立案をする際、CVP分析を取り入れることで、施策により期待される利益について、コストを踏まえた数字で客観的に説明できます。
期待される効果を提示するのはマーケティング施策立案の基本ですが、CVP分析ではコストを固変分解したうえで、それを踏まえて販売量と利益の動きを説明することで、単に効果のみを説明するよりも説得力が出るはずです。
また、損益分岐点表と合わせてCVP分析による数字で説明することで、施策の効果について視覚的によりわかりやすく説明できます。
CVP分析を実践する際の注意点
ここまで解説してきた通り、CVP分析はマーケティングにおいても役立つ分析ですが、その分析結果を戦略や施策などに反映する場合、以下の点に注意しましょう。
CVP分析の計算結果は現実の結果とイコールではない
CVP分析は、比較的シンプルな指標と数式から分析を行います。現実には、コスト・販売量・利益について、CVP分析の指標や数式に落とし込めない要素による影響もあります。
たとえば、商品は製造した分だけコストがかかりますが、製造した商品がすべて売れるわけではありません。あるいは、商品の原価や販売価格は変動することがあります。
そのため、CVP分析と現実の結果には多少なりとも乖離が生じるはずです。それを理解したうえで、CVP分析を活用しましょう。
現実との乖離を小さくするには、商品・サービスごとに分析を行うなど、細かな粒度で模で分析を行うのが効果的です。また、過去のデータに対して分析を行い、分析結果と実際の状態にどれだけの乖離が生まれるのか見ておくと参考になります。
施策ごとの振り返りも並行して行う
マーケティング施策の効果を最大化するためには、PDCAサイクルを回すことが重要です。
施策を実施したら定期的に振り返りを行い、施策立案の際に行ったCVP分析について、実際の結果がどうだったのかも確認しましょう。
分析と結果に大きな乖離がある場合、コストを読み違えている可能性があります。把握できていないコストはないか、また、コストの数字はあっているかを確認しましょう。
コスト削減はその影響を理解したうえで行う
CVP分析を踏まえてコスト削減を検討する場合、CVP分析以外の要素も十分に考慮する必要があります。
CVP分析では、コストを削減すれば利益が増えるように見えるかもしれません。しかし、コストを削減するということは、商品・サービスの品質やブランドの価値、顧客の購買体験に少なからず影響を及ぼします。
それが顧客の購買意欲を削ぐものになってしまうと、コストを削減したものの販売量も減ってしまって利益も減るということになりかねません。コスト削減を行うならば、そうならない範囲と方法を考えましょう。
売上はあるのに利益が上がらない、施策を行ってもなかなか利益が出ないなど、課題に感じていることをぜひお気軽にご相談ください。
CONTACT お問い合わせ
WRITING 執筆
加藤 淳平
経理・財務分野において、事業会社と税理士法人での実務経験を持つプロフェッショナル。
事業会社では経理・財務・経営企画分野で、決算業務、予実管理、予算策定、組織再編、J-SOX対応まで幅広く従事。税理士法人では財務・税務支援業務に加え、財務DDや株価算定業務を担当。
日商簿記1級、全経簿記上級の資格を有し、税理士試験(簿記論)合格。理論と実務の両面から、企業の財務・経理課題に対する深い知見を有する。