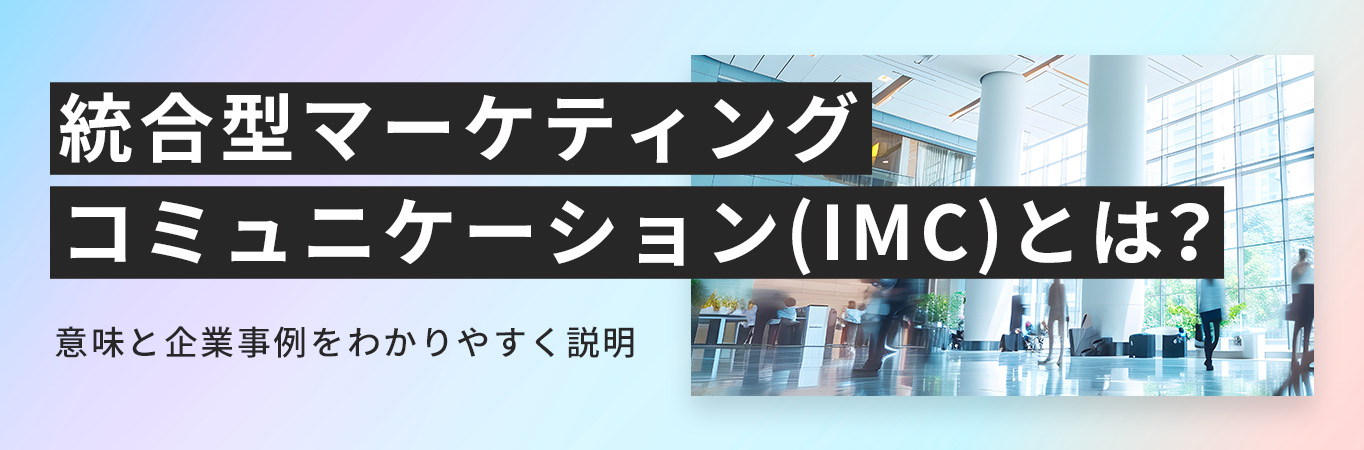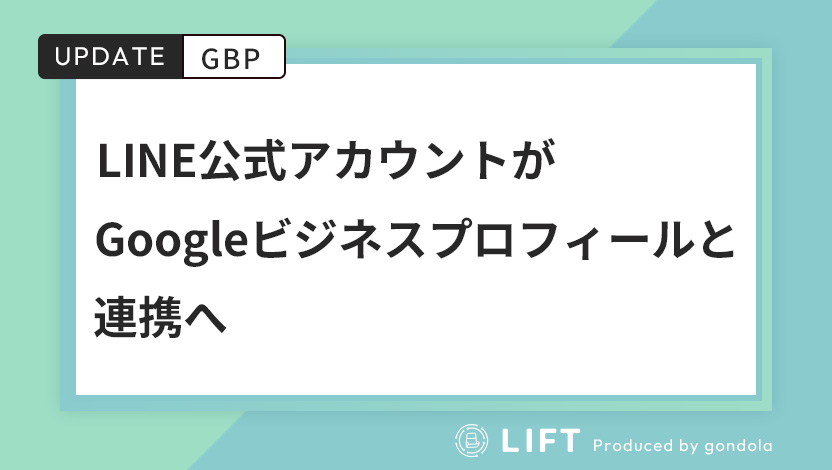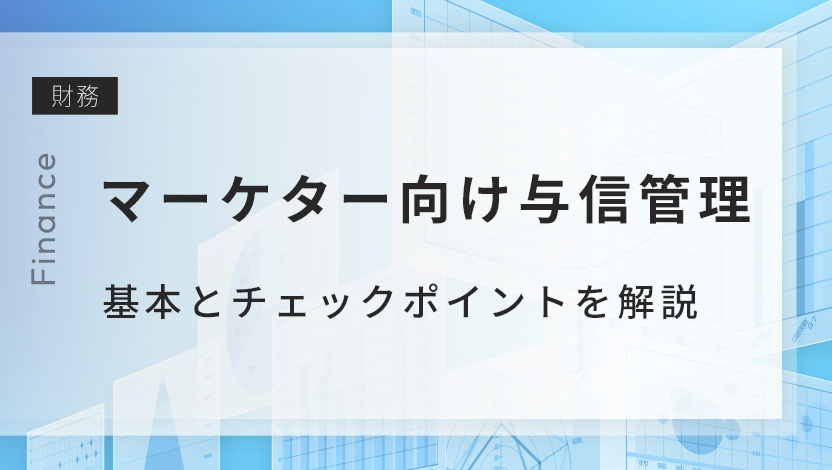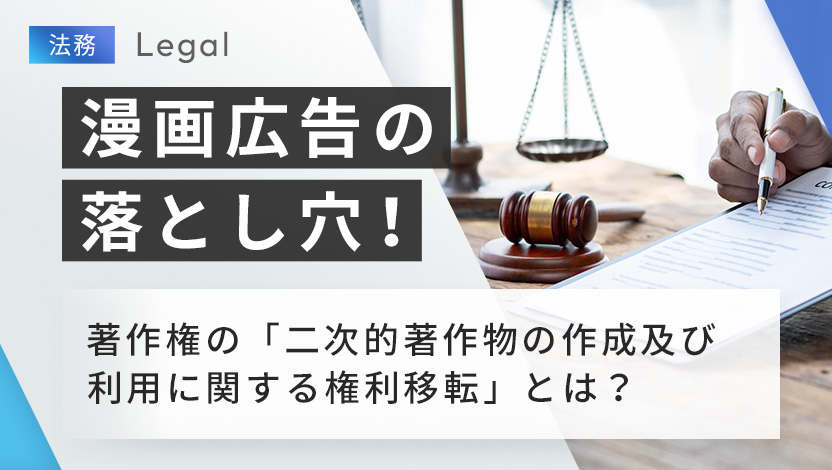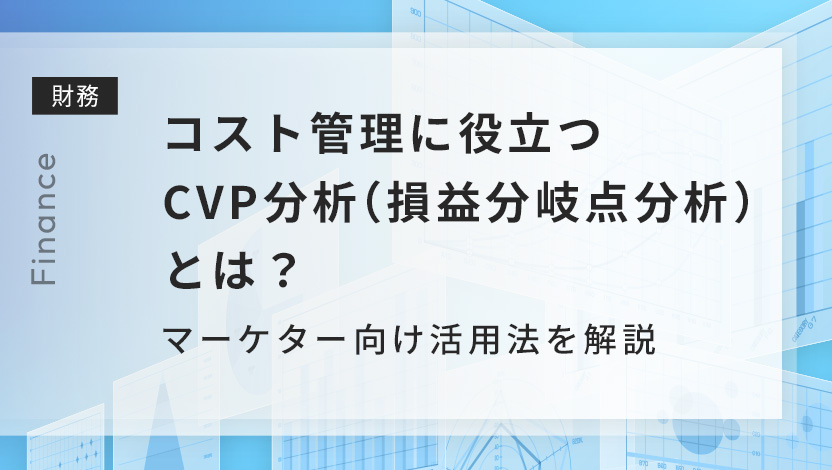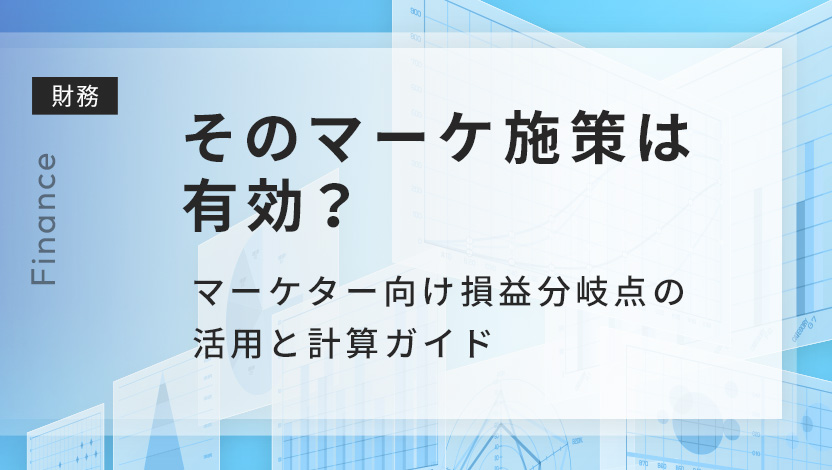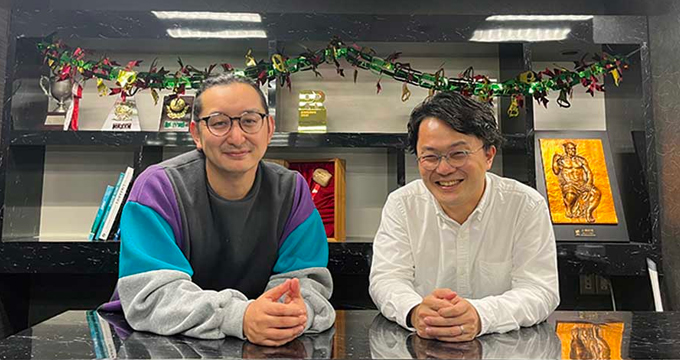統合型マーケティングコミュニケーション(IMC)とは、顧客とのさまざまなタッチポイントを一元管理し、統一されたコミュニケーションを提供する戦略です。この記事では、これから重要性が増していくIMCの意味や実践方法、企業事例を紹介します。IMCは、顧客に説得力のあるアプローチを行いたい企業に欠かせない考え方です。中小企業における顧客との良好な関係性の構築やブランディングに役立つ戦略なので、ぜひ挑戦してみてください。
あれ?先輩、難しい顔をして何を考え込んでいるんですか?
あぁ。ビギニャー君、おはよう。今ね、お客さんのIMC戦略を考えていたんだ。コミュニケーションプランをどうしようかなって悩んでいるんだよねぇ。
IMC…?初めて聞いた言葉ですっ。一体どんな戦略なんですか……?
INDEX目次
統合型マーケティングコミュニケーション(IMC)とは
統合型マーケティングコミュニケーション(IMC)は、企業と顧客の多種多様なコミュニケーションに統一性を持たせ、成果の最大化を目指す戦略です。アメリカのドン・E・シュルツ氏らによって1980年代に提唱された概念ですが、市場の変化にともない、近年一気に注目度が高まっています。
概要だけを聞くと具体的な戦略をイメージしにくいIMCですが、果たしてどのような意味や特徴があるのでしょうか。ここではIMCについてわかりやすく説明します。
- 統合型マーケティングコミュニケーション(IMC)をわかりやすく説明すると?
- 統合型マーケティングコミュニケーション(IMC)が重要な理由
- 統合型マーケティングコミュニケーション(IMC)のメリット
- 統合型マーケティングコミュニケーション(IMC)のデメリット
- 統合型マーケティング(IM)との違い
上記5項目について詳しくみていきましょう。
統合型マーケティングコミュニケーション(IMC)をわかりやすく説明すると?
統合型マーケティングコミュニケーション(IMC)とは、顧客との接点となるあらゆる施策において、統合的かつ一貫性のあるアプローチ・メッセージの発信を行う戦略です。さらにわかりやすくいうと、「いつでもどこでも顧客が同じメッセージを受け取れるように、チームや部署、施策の垣根を越えて統一感のあるコミュニケーションを提供すること」を意味します。
近年は、以前よりも多くの方法で企業と顧客が接点を持つようになりました。店舗はもちろんのこと、各種広告やWebサイト、SNS、カスタマーサービスなど、接点を挙げればキリがありません。IMCでは、それぞれの接点で発信するメッセージや構築する世界観などを統合して、どこで何を体験しても一貫性のある訴求ができるように戦略を立てていきます。
統合型マーケティングコミュニケーション(IMC)が重要な理由
IMCは決して新しく提唱された概念ではありませんが、近年重要性が増してきている考え方として注目されています。その理由として、タッチポイントが多様化・複雑化し、一貫したメッセージを発信することが難しくなったことが挙げられます。
現在、企業と顧客がコミュニケーションを取るチャネルは、次のように多種多様です。
- 実店舗
- マス広告
- チラシ
- DM
- Web広告
- Webサイト
- SNS
- 動画コンテンツ
- メールマガジン
- 電話
- カスタマーサービス
上記のようなタッチポイントにおけるすべてのコミュニケーションを、一部の部署だけで行うことは困難です。そのため、異なった部署・担当者が分担してアプローチすることが一般的でしょう。
しかし、複数の部署が顧客にアプローチする場合、どうしても一貫性のあるアプローチが難しくなってしまいます。その結果、顧客に次のような印象を与えてしまうことは少なくありません。
「テレビCMを見て来店したのに、接客対応がイメージと違ってがっかりした」
「同じ内容のメルマガとDMが届いて、押し売りされている感じがする」
「メディアによって言っていることが違うから信頼できない」
タッチポイントやチャネルによってメッセージが異なると、顧客からの信頼を失ったり混乱させたりする可能性があります。そのため、すべてのタッチポイント・チャネルを一元管理して、統一されたメッセージを適切な頻度で発信する必要があるのです。
統合型マーケティングコミュニケーション(IMC)のメリット
IMCの考え方を取り入れると、企業は次のようなメリットを得られます。
- 信頼関係を構築しやすい
- ブランディングにつながる
- 費用対効果が高い
各メリットの詳細をみていきましょう。
信頼関係を構築しやすい
一貫性のあるメッセージは、安心感の醸成に役立ちます。どのタッチポイントでも同じ理念に基づいてメッセージが発信されていれば、顧客に信頼してもらえる可能性が高まるでしょう。
さらに、一貫性のあるメッセージを発信し続けることで、繰り返し接する物事に対する好感度が高まる「ザイオンス効果」にもつながります。
また、IMCではすべてのタッチポイントにおけるメッセージや施策を一元管理するため、顧客それぞれに適したタッチポイントやメッセージの量を管理しやすくなります。「DMもメルマガも来てしつこい」などという失敗を防げるので、イメージダウンを防止できるでしょう。
ブランディングにつながる
明確で統一性のあるメッセージを繰り返し発信することは、ブランドイメージの確立・浸透につながります。「〇〇社といえば△△」という強い印象を与えられると、競合他社に負けない競争優位性を確立できるようになるでしょう。
伝えるメッセージが多様化すれば、それだけ企業や商品の魅力を多く発信できるかもしれません。しかし、各タッチポイントで担当部署が思い思いに発信しても、情報に情報が埋もれてしまい、すべてのメッセージの印象が薄まってしまいます。
しっかりと顧客の心に残るには、すべてのタッチポイントでひとつのメッセージを繰り返し発信していくことが不可欠なのです。
費用対効果が高い
IMCには、マーケティング施策の費用対効果を高める効果があります。メッセージを統一することで、クリエイティブの制作にかかる手間や時間を削減できるためです。
チラシを作るとき、テレビCMを作るとき、Web広告を作るときなど、すべての施策においてゼロから訴求ポイントやクリエイティブを制作すると、それだけ費用も時間もかかります。しかし、「訴求したいメッセージは〇〇」「起用するイメージキャラクターは△△」「テーマカラーは□□」とあらかじめ決めておけば、スピーディーかつ既存素材でクリエイティブを制作しやすくなりますよね。
またIMCを導入するときは、メッセージの一括配信やオペレーションの簡易化などのメリットも生じます。従来個別に管理・実施していた戦略を統合することで、高いシナジーを生み出せるようになるのです。
統合型マーケティングコミュニケーション(IMC)のデメリット
メリットが豊富なIMCですが、次のようなデメリットもあります。
- 長期的な取り組みが必要
- 運用が難しい
- 制約が多くなる
どのようなことなのか、詳しく説明します。
長期的な取り組みが必要
IMCで成果を出すには、中長期的な取り組みが必要です。すぐに成果を得ることはできないので、ハードルが高くモチベーションも下がりにくい点に注意しましょう。
そもそも、IMCを実現するには各部門との連携や情報共有が不可欠です。なかには、発信するメッセージの設計から始める必要がある企業も存在するでしょう。
さらに、IMCは運用と改善を繰り返すことで効果の最大化を目指すことが前提となる戦略です。社内の体制が整って運用を開始したあとも、戦略が安定するまで長い期間を要することは理解しておきましょう。
運用が難しい
「すべてのタッチポイントでメッセージを統一する」と聞くとシンプルに思えますが、実際に運用するとなると、IMCは非常に難易度が高い戦略です。その理由として、日本の企業では縦割り文化が根強いことが挙げられます。
店舗や営業、マーケティングなどの各部署が分断され、それぞれが自律的に業務を遂行する「事業部制」を取っている企業の場合、連携するための体制を整えることすら難しい可能性があります。それぞれが利益を最大化できるよう、異なった目標や方針を持っているためです。
部門間で連携してIMCを運用する体制を整えるには、組織変革を行ったり全社共通のシステムを導入したりする必要があります。そのためにはマーケティング部門のみならず、経営層や管理層が主体となり、全社を巻き込んでIMCの導入・運用を進めなければいけません。
制約が多くなる
各部門がある程度自由にキャンペーンを打ち出している場合、IMCによってアイデアや施策が制限される場合があります。ときには大きな方向転換を余儀なくされ、チームから不満が出ることもあるでしょう。
また、軸となるコンセプトがいまいちだった場合、すべてのチャネルで成果が出にくくなる点にも注意が必要です。IMCを実施するときは、社内の理解促進や慎重な戦略の立案が必要となります。
統合型マーケティング(IM)との違い
統合型マーケティング(IM)は、ターゲットとなる顧客だけではなく、すべての市場・ステークホルダーを対象にマーケティングを進めていくことが重要であるという考え方・戦略を指します。それを達成する方法のひとつが、一貫性のあるコミュニケーションを提供するIMCです。
とはいえ、IMとIMCの違いは明確に定義されているわけではなく、同じような意味で使用されることも多い言葉です。それぞれの意味を理解しつつ、文脈に応じて柔軟に解釈しましょう。
チャネルによって対応やメッセージが違うと、お客さんが混乱しちゃうよね。だから、すべての接点で同じ対応ができるように、組織や施策を統合していこうねっていう取り組みなんだ。
なるほどぉ。何となく意味はわかったんですけど、具体的な取り組みをイメージしにくいんですよね……。先輩、わかりやすい事例を教えていただけませんか?
そうだね、有名な企業の例を挙げると……。
統合型マーケティングコミュニケーション(IMC)の企業成功事例
IMCに成功している企業の事例を2つみてみましょう。
コカ・コーラ
コカ・コーラは、IMCによって一貫性のあるメッセージの発信に成功している代表的な企業です。
コカ・コーラと聞くと、赤いブランドカラーや「家族や友だち、恋人と過ごすハッピーな時間」をイメージする方が多いのではないでしょうか。これは、コカ・コーラ社が顧客とのあらゆるタッチポイントで、ブランドカラーやハッピーなメッセージを発信し続けているからです。
テレビCMはもちろん、商品パッケージや自動販売機、店頭ポップなどさまざまな接点が統合されている点がコカ・コーラの強みです。そのうえで、自動販売機とアプリを連動させたりSNSキャンペーンを打ち出したりと、オフラインとオンラインのチャネルをフル活用しながら、顧客と効果的にコミュニケーションを取っています。
ユニクロ
ユニクロも、IMCに成功している企業です。
ユニクロのアイテムはベーシックなデザインが基本で、程よいファッション性と機能性の高さが魅力です。店舗や広告、アプリなどもシンプルに仕上がっており、世代やトレンドに左右されない価値を提供しています。
このような一貫性のあるブランドメッセージを発信するために、ユニクロでは「グローバルコミュニケーション部」という部署にマーケティング業務を集約。日本企業の課題である縦割り社会の弱点を克服しつつ、プロジェクトごとに担当者がチームを統率して統合的なマーケティング戦略を実践しています。
なるほど……。たしかに、いわれてみると事例の企業は名前を聞いただけでメッセージや魅力がすぐに思い浮かびます!
でしょう?いろいろなタッチポイントや商品を提供している企業なのに、1つのイメージが思い浮かぶのはすごいよね。IMCに成功すると、こんな風に強い印象を残せるんだ。
へぇ~、すごいですねっ!僕もIMCに興味があるなぁ。先輩、IMCを実施する方法を教えてくださいませんか!?
統合型マーケティングコミュニケーション(IMC)を行う手順
IMCを行うときは、次の手順で準備を進めていくことが大切です。
- ブランドコンセプトを明確にする
- 目的とペルソナを決める
- コミュニケーションプランを設計する
- 効果測定と改善を繰り返す
各プロセスのポイントをみていきましょう。
ブランドコンセプトを明確にする
一貫したコミュニケーションを提供するには、ブランドコンセプトを明確化する必要があります。まずは、軸となる企業理念やブランドイメージ、メッセージなどを設計しておきましょう。
- ブランドを通じて消費者に提供したい価値
- ブランドに対して抱いてほしい印象
- ブランドを象徴する色やモチーフ、デザイン
- ブランドが消費者に与えるベネフィット
- ブランドを表すキャッチコピー
決めておきたい項目の一例としては、上記のようなものが挙げられます。
ここで注意したいのは、すべてのチャネル・タッチポイントでまったく同じ情報を発信すればよいわけではない点です。基盤となるブランドコンセプトを反映しつつ、各チャネルに応じたメッセージを伝えていくことが大切です。
IMCでは関連部門の連携が不可欠なので、各部門のメンバーで協力しながらブランドコンセプトを整理し、認識をすり合わせておく必要があります。決定した内容は、関わるメンバー全員で共有しておきましょう。
目的とペルソナを決める
次に、IMCを実施する目的とペルソナを決めましょう。
IMCの目的としては、長期的なブランディングや収益増加、顧客満足度の向上などが挙げられます。目的を達成したい期限についても設定できると、具体的なスケジュールを作成しやすくなるでしょう。
ペルソナ設計は、一貫性のある訴求や施策の実施に欠かせないプロセスです。ブランドのターゲットになる具体的な顧客像を整理して、ライフスタイルや課題、心理状況などを詳細に把握していきます。
ペルソナをしっかりと設計できると、各部門が異なった顧客像を抱き、メッセージの方向性がズレてしまうことを防げます。また、具体的なタッチポイントや心理変化を追えるようになるので、次に行うコミュニケーションプランの設計をスムーズに行いやすくなる点もメリットです。
コミュニケーションプランを設計する
ここまで整理した情報をもとに、具体的なコミュニケーションプランを設計していきましょう。この際、消費者と接触するタイミングやチャネルをフェーズごとに整理できるよう、「カスタマージャーニーマップ」を活用することがおすすめです。
コミュニケーションプランの設計で決めておきたい内容としては、次の3つが挙げられます。
タイミング
まずは、企業と消費者が接触するタイミングを整理します。
- 商品リリースの前段階
- リリース後の認知拡大段階
- 情報収集段階
- 比較・検討段階
- 購入段階
- リピート促進段階
上記のように、企業と消費者には無数のタッチポイントが存在しています。各フェーズでペルソナがどのような課題を抱えどのような行動を取るのかを整理して、最適な情報提供のタイミングを見極めましょう。
チャネル
消費者と接触するチャネルも決めておきたい重要な要素です。
そもそも、消費者のフェーズによって企業と接触するチャネルは大きく異なります。商品認知段階であれば広告や店頭、比較・検討段階であれば自社メディアやSNSなどが主なチャネル候補として挙げられるでしょう。
IMCで重要なのは、顧客の心理・行動に応じてチャネルを最適化していくことです。チャネルごとに対象者や獲得したい効果を整理し、ターゲットを狙い撃ちできると効果的です。
内容
タイミングとチャネルが明確になったら、あとはメッセージの内容を決定するだけです。各フェーズにおける消費者を次の行動につなげるにはどのようなメッセージが必要なのか、顧客目線で設計していきましょう。
メッセージの内容は、決して宣伝文句やキャッチコピーだけではありません。ブランドコンセプトを象徴するデザインや世界観の構築、体験の提供など、五感に訴えかけるメッセージの発信も重要です。
また、各チャネルで発信したメッセージを共有できるように、MAツールやCRMなど情報共有に役立つシステムを導入しておくことがおすすめです。
効果測定と改善を繰り返す
IMCの実施を開始したあとは、定期的に効果測定を行いましょう。ブランドコンセプトが正しくターゲットに届いているか、メッセージの発信方法・内容にズレはないか、問題は生じてないかなどを各部門で連携しながら検証します。
IMCの成果は数値化しにくいため、正確に効果測定を行うのは容易なことではありません。売上や会員登録者数などの定量的な指標はもちろん、ブランドに抱いているイメージや好感度などの定性的な指標に関しても調査を行い、多角的な視点で評価していくことが大切です。
課題や問題点があれば、改善策を考えます。このとき、マーケティング部門だけではなく、関連部署全体で課題や改善策を共有することがIMCを成功に導くためのポイントです。
こんな感じかな。一貫性を意識しつつ、ペルソナの行動や心理に応じたコミュニケーションプランに仕上げていくことが大切だよ。カスタマージャーニーマップとかで可視化しながら進めていくと、思考を整理しやすくなるよ。
とっても勉強になりますっ!IMCって組織体制の変革とかシステムの導入とか、リソースがある企業向けの戦略っていうイメージがあるんですよね。中小企業でも成功させることってできるんですか?
そうだねぇ。こういうポイントを意識すると、中小企業でもIMCを成功させやすくなるよ。
中小企業がIMCを成功させるポイント
IMCを実施するときは、複数チャネルの活用や各部門の連携体制構築、社内全体を巻き込んだ組織改革など、多くの取り組みが必要です。そのためには多くの人的・金銭的リソースがかかるため、中小企業でIMCを成功させることは難しいと思われるかもしれません。
しかし、取り組み方を工夫すれば、中小企業でも効果的なIMCを実施することは可能です。中小企業がIMCの効果を高めるために意識したいポイントは、次の4点です。
- スモールスタートにする
- SNSで交流を生み出す
- 顧客目線でコミュニケーションを設計する
- 一貫性のあるアプローチを徹底する
各項目の詳細をみていきましょう。
スモールスタートにする
IMCに取り組むときは、スモールスタートを意識しましょう。いきなり大きな成果を狙ったり大規模な変革を行おうとすると、社内調整に時間がかかってプロジェクトが停滞しやすくなるためです。
IMCを継続するには、小さな成功体験を重ねて関連部署と戦略のイメージを共有することが大切です。
初期段階におすすめの施策としては、CRMなどのファーストパーティデータを活用することが挙げられます。既存の顧客情報を分析・活用して顧客ニーズや行動を分析すると、ブランドコンセプトやペルソナ、コミュニケーションプランを設計しやすくなります。
IMCのために新しいシステムや取り組みを一気に始めるのではなく、既存のリソースやシステムで取り組めることから始めてみると失敗を防ぎやすくなるでしょう。
SNSで交流を生み出す
IMCにおいて、双方向のコミュニケーションが取れるSNSの役割は非常に重要です。X(旧:Twitter)やInstagramなどのSNSは、積極的に活用しましょう。
企業が情報を発信することでブランディングやファン化につなげるだけではなく、ユーザー同士のコミュニケーションの中で企業価値の向上を目指すことが大切です。消費者同士の自発的な交流はブランドへのロイヤルティ向上に効果的ですし、マーケティングに役立つアイデアの獲得にもつながります。
ただし、すべてを消費者に委ねているだけでは、SNSでの交流は生まれません。「あなたはどっち派?アンケート」「おすすめアレンジ活用術を募集」など、企業が交流のきっかけを作り出してあげることが大切です。
消費者の交流にはしっかりと目を通し、積極的に意見やアイデアを吸い上げて施策に反映しておきましょう。
顧客目線でコミュニケーションを設計する
IMCでは、顧客ニーズにマッチした価値提供が大切です。ブランドコンセプトやコミュニケーションプランを設計するときは、企業の一方的な価値観に偏ってしまわないように注意しましょう。
ニーズに沿わないメッセージの発信は、顧客から反感を買うリスクを高めます。情報を提供するときだけではなく、商品開発やカスタマーサポートなどすべてのプロセスにおいて顧客目線を意識することが大切です。
一貫性のあるアプローチを徹底する
一貫性のあるアプローチは、IMCにおいてもっとも重要なキーポイントです。発信するメッセージはもちろんのこと、デザインやスタッフの対応品質、ユニフォーム、パッケージなどすべての要素に統一性を持たせるよう意識しましょう。
開発者・提供者目線だけだと、正しく判断できない可能性があります。アンケートや街頭調査などを活用しながら、消費者目線で一貫性のあるアプローチができているかを確認しながら進めましょう。
いきなりIMCに100%舵を切る必要はなくて、できる範囲から始めれば大丈夫だよ。特にSNSは、コストが低い一方で高い成果を得られるおすすめのチャネルなんだ。一貫性のある対応を徹底しつつ、積極的に活用していこうね。
難しく考えすぎていましたが、スモールスタートでもいいなら中小企業でも取り組みやすいですね!先輩、いろいろと教えてくださってありがとうございました!
どういたしまして。ビギニャー君と話していたら、僕も思考を整理できたよ。さっそく、お客さんに戦略を提案してこようっと。
CONTACT お問い合わせ
WRITING 執筆
LIFT編集部
LIFT編集部は、お客様との深いつながりを築くための実践的なカスタマーエンゲージメントのヒントをお届けしています。